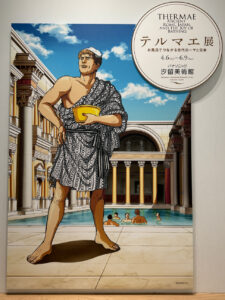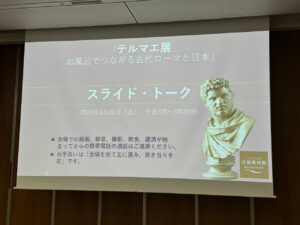「名取と行く那須どうぶつ王国日帰りツアー」を利用して、那須どうぶつ王国に行ってきた。
名取が何か全く知らないし興味もないのだが、新宿からバスで直行し、現地に5時間半滞在後新宿に戻るだけという、本当に那須どうぶつ王国で遊ぶ事に特化したツアーだったため、参加してみる事にしたのだった。
実は那須どうぶつ王国は車がないと大変行きにくい。
一応最寄り駅は新幹線の那須塩原、黒磯、新白河のどれかという事になるのだが(距離的には新白河が一番近そう)、路線バスが全くない上に、送迎バスも開園と閉園に合わせて1日1往復、那須塩原駅から出るだけで、しかも片道1時間以上かかる。
そんな那須どうぶつ王国に、新宿からバスで往復できるのだ。これはもう名取が何かを差し置いても参加するしかないではないか。

来た!
名取とはVtuberで、バスに乗っている間、往復合わせて計2時間ほどガイドと称した自分語りや歌(の録音放送)を聞く羽目になったが、それが意義のコラボツアーらしいのでそこはまあしょうがない。
とりあえず、着いてしまえばあとはこっちのものなのだ。

まずは入口からすぐ、ニホンリスが放し飼いされている屋外禽舎に入ってみる。
なお、今回はいつものキヤノンのコンデジではなく、ソニーのα6000にタムロンの18-300をつけた物を持ち込んでみた。
考えてみたら、自衛隊関係以外に本格ズームつきのミラーレスを持っていったのはこれが初めてじゃないだろうか。

手をちょっと出せば触れるぐらいの所にリスがいる。
もちろん触ってはいけない。そっと見るだけ。
なお、王国内は、入口からすぐの主に室内展示を中心とした「王国タウン」と、少し離れた家畜の屋外展示と野外パフォーマンスが見られる「王国ファーム」のふたつのエリアで構成されている。
要するに上野動物園と同じ構造なのだが、上野と違って2エリア間にはかなりの高低差と距離があり、歩くとちょっとしたハイキングになってしまうため、移動するには専用のバスまたはリフトとトラクターバスを使う必要がある。
とりあえずはタウンをひとまわりしてみようか。

プレーリードックちゃん。
敷地全体で多分100匹以上いるのではないか。

そしてその格好はどうなのか。

次に、熱帯の森という建物に入ってみる。
外にケア(ミヤマオウム)のケージが併設されていて、窓から何をやっているのか見ることができる。
思ったより小さい。ボウシインコぐらいの感じ?
なんかこっちを眺めていた。

ガマグチヨタカが寝てい……るふりをしてこっちを見ている。
実物初めて見たわ。

2羽いた。

ミナミコアリクイ。かわいい。

ピグミーマーモセットは放し飼い。

オオバタンも放し飼い。

羽繕いしているオウギバトと挟まっているリクガメ。
放し飼い多いな?!

建物の中央には池がしつらえてあって、グッピーとかが泳いでいる。
50センチはありそうな巨大なリュウキンがいるなと思ったら、ヒレナガニシキゴイというコイとのこと。
確かにヒゲがある。そしてヒゲまで長くて枝分かれしている。
なんだこの生物……。

フタユビナマケモノも放し飼いだが、さすがに池で客とは隔てられている。
大人しいんだけど爪がね。うっかり子供とかがちょっかい出して掴まれちゃったりしたら大惨事になるからね。

もう1回ケアを見たら寝てた。
もふもふ。
次に入ったのがウェットランドという建物。
ここも熱帯の森同様、鳥や動物がほぼ放し飼いされている中を人間が歩きながら見ていく形になっている。

入った途端に飛んできて交尾を始めたカモのカップル。
もう1羽いるオスは多分割り込みたくてチャンスを狙っている。

足。

エルフ耳のイノシシ。
アカカワイノシシというらしい。こんなイノシシいるんだ……。


いろいろいる。

卵だって抱いてる。

多分ミゾゴイ。

なんか仕切りの上とか壁際とかにもいっぱいいた。

ジャガーはさすがに隔離されてた。

わちゃわちゃしているコツメカワウソ。
固まってぎゅっとなったり水中で組んずほぐれつの追いかけ遊びをしたり、かなり活発だった。
テレビでも時々やっているのでそこそこ知られていはいるが、このどうぶつ王国では、稀少動物の保存や繁殖に力を入れている。
次に入ったのはそういった動物が集められている保全の森という建物。

ツシマヤマネコ。窓際で寝てた。

スナネコ。
実家の猫もこんな感じで寝てるな……。

ニホンライチョウ(夏仕様)。

こちらは上野動物園にもいたスバールバルライチョウ。
かなりの高齢なのだそう。だから首の後ろがハゲているのだろうか。

アムールヤマネコ。ポーズや表情がいちいち凜々しい。
とそんな感じで見ていたら、ファームでやる鳥のパフォーマンス「BROAD」の時間が迫ってきたので、移動することにした。
バスかリフトか迷った挙げ句リフトを選択したのだが、これが大正解。

涼しい風と緑の中を空中散歩。
リフトは音がしないので、鳥のさえずりや木のざわめきまではっきりと聞こえてとっても気持ちがいい。

リフトを降りると次はトラクターバス。小岩井牧場でも乗った奴。
急坂をグイグイ行くので楽しい。
そんな訳で会場に到着。

鷹匠の要領で訓練された猛禽類が、縦横無尽に飛び回るパフォーマンス。
すごく低い所を飛んでいくのでかなりの迫力。


ミミズクだって飛ぶ。


獲物を空中で捕まえるパフォーマンス。

ヨウムはものまねを披露。
男の人が訓練したのか、名前がシルヴィアなのに言葉が完全に男性のダミ声なのがちょっと面白かった。
これも登場の時はちゃんと飛んでくる。とまっている時には分からない赤い尾羽がとても鮮やかだった。


多分敷地が広いからできるハクトウワシの飛翔。
2メートル以上もある鳥が、数百メートル離れた森からこっちに向かって飛んでくる。


ハヤブサの狩りパフォーマンス。
疑似餌につけてた肉をあっという間に食べちゃって、もっと欲しそうな顔をしているのがかわいい。


最後はコンゴウインコの飛翔。
緑の森を背景にした巨大で色鮮やかなインコがとても印象的で、そういえばうちのセノーテが飛ぶのは、恐いものから逃げたい時ぐらいだなあと思いながら見ていたら、なんだか分からないけれどちょっと涙が出てきた。
航空祭で飛行機を追っているので、鳥ぐらい余裕と思っていたのだが、前の方に座ってしまったのでうまくカメラで追い切れず、結局ピンボケ写真ばかりを量産する羽目になってしまった。
後ろの列に座るべきだったなこれ。

最後に鳥たちがお見送り。
この子はショーには出ないが、人に慣れるよう連れてこられていた。
肉をむさぼっていてそれどころじゃなさそうだったけど。

ショーのごほうびにおいしいものをたくさんもらったコンゴウインコ。

ばんざーい。
とりあえずショーを堪能したので、ファームをぐるっと回ってタウンに戻るとするか。


ショー用以外にも猛禽が結構いた。
コンドルになぜかガン見される。


馬とかラクダとか。


子羊かわいい。
どこに目があるのか分からないけどかわいい。


丁度牧羊犬のパフォーマンスに行き当たったので、ちょっとだけ見てタウンに戻ってきた。
なお、帰りもトラクターとリフトを使いました。だって楽しかったんだもん。

さてBROADを見るために中断した所から見るか。
……マヌルネコだった。

いつ見てもでかいアムールトラ。

カワウソ。何のカワウソかは忘れた。

もう何の動物かすら分からない。

レッサーパンダ。

山の中なのになぜかペンギンが大量にいる。
餌やり体験もできる(やった)。
切った小アジをトングで投げ与えるのだが、高く掲げてやるとみんなぐぐぐっと前のめりになるのが面白い。

手を伸ばせば触れる場所でエサをねだっているのだが、近すぎて逆に目に入れてもらえない可哀想なペン。

これもなぜかいるゴマフアザラシ。
飼われているのは淡水だろうか、海水だろうかとどうでもいい事が気になったりして。

パフィン。明らかにカメラを恐がっているんだけど、でも好奇心もあって目が離せないでいる。
曇っているのはアクリル板が傷だらけのため。

もう1回保全の森に行ったら、ツシマヤマネコが起きてた。

スナネコも起きてた。

ライチョウはなんかすごいこっちを見ていた。
そういえばライチョウは人を恐がらないんだっけ。

エサの時間が近いのか、飼育員さんが出てくる扉のあたりをひたすらうろうろしているスバールバルライチョウ。

野生の目。

鳴くケア。

羽繕いするケア。

ボウルで遊ぶケア。

止まり木に移動したケア。

のびをするケア。
ひたすらケアを見ているところで時間終了。
楽しかった。
基本的に動物達は放し飼いになっていて、その中に人間が入っていくという形になるので、すごい近い目線で動物のことを見られる。
また来たい。でもどうやって来るかが問題だな……。
○おまけ

気持ちは分かるがそれはオカメインコではない。