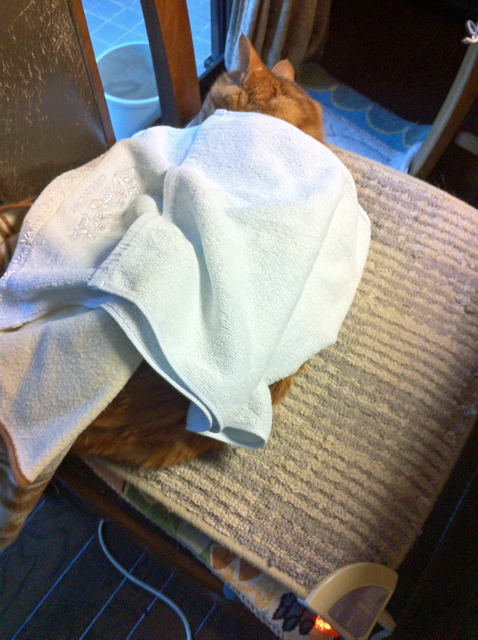うたたね
白いカメラ
NIKON1のV1、ダブルズームキットを買った。

白にしたのは価格comで黒より5000円ぐらい安かったから。
でもこの時が底値だったらしくて、買った翌日見たら一気に1万円値上がりしていた。
印象としては、とにかくマニュアルがわかりにくいということ。
冊子の「簡単スタートガイド」と「使用説明書」のふたつがあるのはまあ良くある仕様だが、今回はさらに詳細な設定等をしたい場合、CD-ROMのマニュアルを参照しなくてはならない。
しかも、この設定の方法がどのマニュアルに書いてあるのかというのが分からないので、いちいち冊子版の使用説明書見て、なければCD-ROMのマニュアル見てということの繰り返しになる。
複数のマニュアルの媒体が違うってこれほんとイライラする。
全部冊子かCD-ROMにまとめてほしい。
で、例によって鳥どもで試し撮り。
画質が悪いのはカメラのせいではなくて、そもそも無茶な設定をしているから。




NIKON1のシリーズは焦点距離が普通の一眼デジカメの2.7倍だそうで、要するに、同じ焦点距離のズームレンズなら2.7倍でっかく撮れるということらしい。
つまり、今持っているTAMRONのB008も、V1につければ2.7倍でっかく撮れるレンズに変身ということ(なのか?)。
多分、というか絶対に、そんなの航空祭ぐらいでしか必要ないと思うけど、一体どんなことになるのか、ちょっと楽しみ。
いやん来ないで
小さくすねる
最近の鳥猫模様
ほら、掴んでるよ
黄金の鷲の下に
「第九軍団のワシ」を見てきた。
有名な児童文学作家の作品が原作だそうだけど、実は原作も映画の存在も金曜日まで全く知らなかった。
たまたまSFマガジンを数年ぶりにぱらぱら立ち読みしてたら、裏表紙にこの広告があって、なんとなく興味が湧いたので行ってきた次第。
ハドリアヌス帝の時代に、ブリテンの蛮族制圧のために出撃したまま忽然と姿を消したというローマ第9軍団の故事(実際には、記録が残っていなくて行動が不明ということらしいけど)を元にした話。
この時の軍団長の息子であるマーカス・フラヴィウス・アクイラが20年後、父の汚名を晴らそうとブリテンのローマ軍基地に赴任。だが蛮族との戦闘で戦功を立てたものの負傷しあえなく名誉除隊。がっくり来ていたところへ、第9軍団の黄金の鷲の旗印を蛮族が持っているという話を聞き、ブリテン人族長の息子で、ローマを憎んでいるが命を救ったマーカスには忠誠を誓うというややこしい奴隷の青年エスカをひとり連れて取り戻しに行くという話。
ちなみに、ローマ軍では旗印は名誉の象徴とされ、これを敵に奪われるのは軍団にとって最大の恥となる。逆に、敵にとっては旗印を手に入れることは、ローマに勝利したという輝かしい証になる。
なにしろ上映してるのはインディーズ系の映画館、しかも各県で1館程度しか公開館がないような映画なので、なんかすごい癖の強い作品だったらどうしようと思っていたのだが、普通に面白かった。シネコンとかで全国ロードショーしていいレベル。
元が児童文学ということで、ストーリーは単純だし、映画の尺に合わせるためか若干ご都合主義な部分も見えないでもないけど、まさに根本から異なる「異文化」であるローマとケルトの対立の深さとか、ローマ軍がなぜ強かったのかが良く分かる戦いかたとか、マーカスとエスカの安定してるんだか不安定なんだか良く分からない関係とか、いろいろ手を抜かずにきちんと描いている(ように見える)。
難を言えば、最後の最後のふたりのやりとりが、なんだかローマじゃなくてアメリカーンな感じになっちゃってたこと。脚に廃兵にになるほどの大きな怪我をしたはずのマーカスが、平気で馬を乗り回していること、馬に鐙と轡がしっかりついていたこと、が気になった。
もっとも、鐙と轡については、ローマ時代のようにそれなしで自由に馬を操れる人が存在しないと思われるので、仕方ないというのはあるのかも。