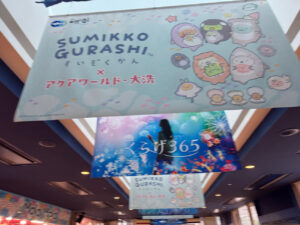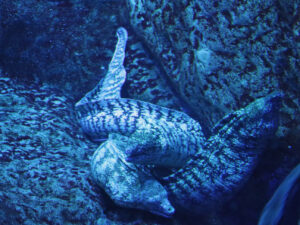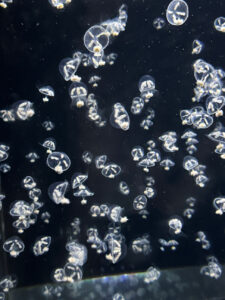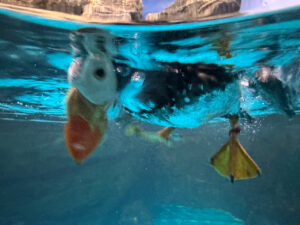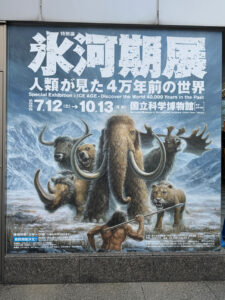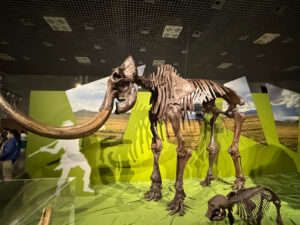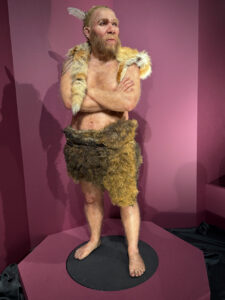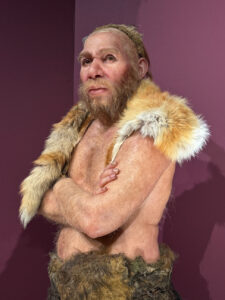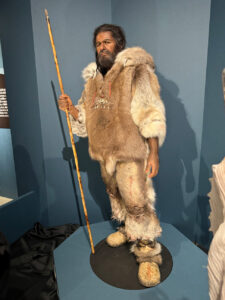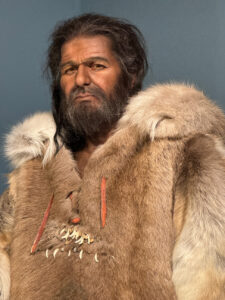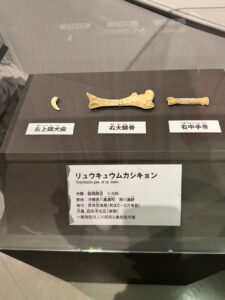9/12、13と上高地に行ってきたため、後追いでアップします。
2日目は朝7時に徳沢に向けてホテルを出発。
ホテルの朝食時間より前の出発になるのでお弁当を頼んだら、おにぎり弁当に加えて行動食用のバナナとソイジョイまで入れてくれていた。

朝霧の梓川。
ここだけ見るとひとけもなくてひっそりしているようだが、実はすでに数百人が河童橋の周囲をうろついている。
朝の風景を目当てに散歩している宿泊組と、早朝到着のバスツアーの人が混じってるっぽい。
朝7時でこれか……。

まずは昨日と同じコースで明神まで歩く。
天気予報では雨となっていたので、降り出した時のためにレインウェア上下はもちろん、傘まで持ってきているのだが、今のところ降りそうな気配は全くない。

昨日のオシドリがまたいた。
よく見ると風切羽も伸びてないし、この後頭部のぽやぽやっぷり、やっぱりまだ親離れしたてのヒナじゃないかな。
ということは、メスじゃなくてオスの可能性もあるのか。

相変わらず、すぐ近くで写真を撮りまくる人間達の事など気にもしない。
かわいい。
なお、この時いたのは1羽だけだったが、数分歩いた場所でもう1羽がやっぱりエサを探していた。
マガモみたいに群れで行動するわけじゃないんだ。

1本だけ真っ赤な幹の木があった。なんだろう。
写真だと茶色みが強くなっているが、現物は本当に赤だった。

カラの混群がいるっぽくて、いろんなさえずりが聞こえてくる。
これはシジュウカラかな……? ネクタイ模様が見えないので分からない。

ゴジュウカラ! 初めて見た!
結構な近さで地面をついばんでいたのだが、まわりの砂利に全部ピントが吸われてピンボケ写真しかなかった。
なるほどこれが自然界の保護色。
そうして1時間ほどでまた穂高神社奥社に到着。
バナナを食べて小休止したら、梓川を渡っていよいよ徳沢へ。

天気予報あ相変わらず雨だが、なんだか雲が切れて晴れだした。
晴れてくるとそれはそれで困るんだよな。暑いし日焼けするし。

徳沢への途中に、1.5億年前の頁岩の岩盤があると聞いて楽しみにしてたんだけど、これかな?
看板とかガイドとか何もないから良く分かんないけど、他に巨大な岩盤は見当たらないし、いかにも長い年月経てきた雰囲気がするし、これな感じ。
1.5億年前というとジュラ紀か白亜紀ぐらいか。人間どころか哺乳類もまだ居なかった頃かな。鳥はもういたっぽいけど。すごいなあ。

なんか木の幹をぴょいぴょい上がり降りしている鳥を発見。キバシリではないっぽいし、ゴジュウカラかな?
ゴジュウカラも木を垂直に上下移動できるらしいし。

視界が急に開けて真っ白な山が見えた。前穂高らしいけれど雲に隠れちゃってる。
実はここまでひたすら変わり映えのしない林の中をてくてく歩くだけで、あんまり面白くないしそろそろ飽きてきていたのだ(だから写真も少ない)。
多分春とか夏なら、いろいろ花が咲いていたりして楽しいのかもしれない。
これが見えると徳沢ももう近いらしいから、あと少し頑張ろう。

到着した!
これが小説に名高い徳沢ロッジかあ。読んだことないけど。
徳沢は昭和の初めぐらいまで牧場だった場所で、その平地を利用して今はキャンプ場になっている。
広い平地に色とりどりのテントが張ってあるし、なんかこう、河童橋から2時間歩くしかない場所とは思えないぐらい、人がたくさんで賑わっている。
でもそれだけ人がいても静かなのは、来ているのが外国人も含めて、ルールを分かったある程度ガチな人ばかりだからか。

トリカブトの花。上高地には結構咲いているのだけど、これが一番青が濃くてきれいだった。

売店兼食堂兼宿泊施設。
丁度昼時だったのでカレーが食べたかったのだが、現金かPayPayしか使えないので諦めた。実は来るときお金を下ろし損ねて持ち合わせが少ないのだ。
クレカと交通系で何とかなると思ったのだが、山はそう甘くはなかった。
まあそんな訳ですっかり満足したので、そのへんのベンチに座ってのんびりだらだらすることにした。
余裕があればさらにこの先の横尾まで足を伸ばしたかったんだけど、さすがに帰りのバスに間に合わなくなる。
あと1時間早く出れば何とかなるかな。今度検討してみよう。もう来るかどうか分からないけど。
そんなこんなで1時間ほどだらだらしていたら、何だか雨が降り始めた。
そういえばずっと森の中を歩いていたから分からなかったけど、いつの間にか雲が厚くなっている。
じゃあそろそろ河童橋まで戻ろうか。また2時間歩くけど。

もう1回山を撮っておこうっと。
ここまで来ないと撮れない風景だし。

去年見たガレ沢は、とうとう砂防ダムみたいになっていた。
6月にはまだ林だったのに、変遷が激しすぎる。

河童橋についた時は結構な本降りになっていた。
ベンチのまわりをうろついておこぼれを狙うキジバトもびしょ濡れになっている……というか、なんでそんなに濡れてるの?

ようやくクレカが使える地域になったので、遅い昼を食べようと思ったのだが、河童橋付近はどこも行列ができていて入れない。
仕方なくバスターミナルのレストランまで戻る事にした。
これは途中で出会ったセグロセキレイ。
とりあえず、これで上高地で行ける所は全部行った感じ。
なんだかんだでお天気もぎりぎりまでもったし、いろいろ鳥も見れたし楽しかった。
雪の降る頃も1度見てみたいけど、きっと無理だろうなあ。