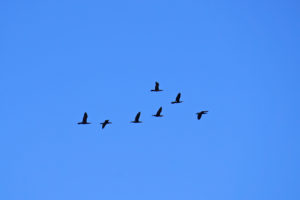百里基地航空祭(特別公開)と自衛隊音楽まつりをハシゴしてきましたが、さすがに疲れたらしく頭痛がするので後でアップします。
復活しました。
というわけで、百里基地航空祭(特別公開)と自衛隊音楽まつりに行ってきた。
特別公開というのは、一般公開の前日に近隣住民限定で希望者に公開される事前予行。知人が基地側から招待され、域外の人も同伴可ということで連れていってもらった。
なお、百里基地の最寄り駅、石岡駅から今回音楽まつりをやる代々木体育館最寄り駅原宿まで、常磐線特急を使えば約2時間。基地祭が14時半終了なので、基地祭名物大混雑をなんとかかわして頑張れば間に合う計算ではある。


時刻は7時。朝日を浴びるブルーインパルスとF-4ファントム。
というか寒い。気温は氷点下3度らしい。
ファントムは実に50年以上に渡って使われてきた機種で、おじいちゃんと呼ばれて親しまれているが、さすがに耐用年数やらなんやらの関係で今年度いっぱいで全機退役が決まっている。
なので、こういう姿を見られるのはこれが最後。


偵察機型。カラフルなのは迷彩。

ファントムを見ていたら、海自のP-1が展示されに厚木から飛んできた。

百里基地でP-1がブルーインパルスの後ろを通っていくという、割とシュールな風景。
ついでに、左端に見える山は筑波山。雲一つないのでブルーがスモーク引いたら筑波山からでも見えそう。
ちなみに、丁度P-1と重なる位置にあるブルーの垂直尾翼に番号がないが、どうやら不具合で代替機を使っているかららしい。




始まるまで1時間半以上あるので、展示機をぶらぶら見に行ってみる。
四季のモチーフをペイントしてあるF-2がきれい。



正面顔シリーズ。ずんぐりしたのがC-2、しゅっとしたのがP-1、まっすぐなのが多用途支援機というふんわりしたカテゴリのU-4。


基地防衛用の対空砲も展示してた。


オープニング飛行の準備のためにタキシングに入るファントム。


次々と離陸していく。

ついでに茨城空港から特別塗装のスカイマークも離陸。


オープニング飛行が来るまでの間観覧車(とプログラムには書いてある)でも撮っていよう。
F-35の方はミサイル積んでたりブルーの方は実機と機体番号をちゃんと合わせていたり、無駄に作りが細かいな……。

オープニング飛行来た!
この百里基地でしか見れない、しかも今年が最後のファントムの6機編隊飛行。
ていうか全機増槽つけてるんだけど、今日は一体どれだけ飛ぶつもりなんだろう。
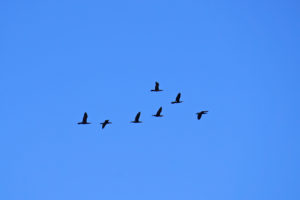
そしてファントムが通り過ぎた直後にやってきた別の編隊。
かなり受けてた。

遙か上空を飛ぶ民間機の近くを通り過ぎるファントム。

そして着陸すると出てくるかわいいパラシュート。
大好きなんだけど、これも今日で見納めかー。


続いて百里救難隊によるいつもの救難展示。
災害が増えてるから大変そうだな、彼らも。

どれだけたくさんの機種を1枚の画面に入れられるか試してみた結果。
右のF-15が切れたのが悔やまれる。

ずらりと並んだサメ顔ファントムと、高度を下げて着陸していくH-60の後ろ姿。
他の基地だとすーっと垂直に降りる事が多いから、こんな風に固定翼機みたいな角度で着陸するのはちょっと珍しい。

F-15。
今日はファントム祭りなので、飛んだのはこの1回だけ。


そしてブルーのパイロットが整備員と一緒に搭乗準備をし始めた。
この基地祭ではブルーは午前中に飛ぶ。
観客がブルー目当てとファントム目当てに明確に二分されるので、ブルー目当ての客を早めに帰して混雑の分散を狙っているのではないだろうか、と思うが定かではない。
ブルーといえば、救難展示の間、1人だけ展示には見向きもせず全然違う方向にカメラを構え続けている多分アラサー女子が近くにいて、何だと思ったらブルーを整備する整備員をひたすら撮り続けているのだった。
しかも大きなズームレンズで、整備員の一挙手一投足を、執拗に何枚も何枚も。
なにそれこわい。
閑話休題。

準備を終えて手を振りながらタキシングしていくブルー。
そういえば、プログラムには通称儀式ことウォークダウンがあったが、実際にはそんなものやらずにパイロットたちはさっさと乗って出発してしまったな。
本番じゃないからかな?
まああれ退屈なだけなんで、ないならないで全然かまわないというか、むしろありがたいんだけど。

タキシング中の全機尻。
誘導路の場所と角度によっては見れないちょっと珍しい構図。

……と思ったら、滑走前の最後の点検で3番機に異常が見つかったらしく、今回の展示は5機体制となった。
5機が離陸した後、とぼとぼと戻ってくる3番機。
パイロット一番張り切ってたのになあ……気の毒に。
とはいえ1機足りないだけで、天候には全く問題なかったので、プログラムは6機いないとできない星とかを除いて予定されていたものは全部実施になった。

整備員に囲まれる3番機の上空を粛々とスモークを吐いて通過していくブルーインパルス。


しかしやっぱり1機足りないと微妙にバランスが悪い。

そして地上ではただごとではない感じになっているが大丈夫か。


太陽光の加減か、スモークの陰影が強調されて絵画みたいな雰囲気になっている。
入間ではこんな写真撮れたことないな。太陽の高さとか関係するんだろうか?

筑波山とブルー。

これまで狙っても撮れなかったタッククロスに初めて成功。

2番目に好きなやつ。
ちなみに1番好きなのはコンバットブレイクだが撮り損ねた。


帰ってきてからもパイロットたちは無造作に退場していった。
ちなみに3番機のパイロットもさりげなく混じって帰って行った。


午後はファントムの独壇場。
模擬スクランブル発進と機動。黄色いのは特別塗装機。
スクランブル機動では、上の方で写真を撮った対空砲(写真とは別のもの)が上空のファントムを空砲で迎撃し、対するファントムは爆撃とバルカン砲の地上攻撃動作を行うという大変シュールな模擬戦闘が行われた。
実は対空砲見たかったのだが、距離が離れていていけなかった。残念。

そしてトリを務めるのはまた偵察型。



同じ頃、地上では3番機がひっそりドナドナされていっていた。


パラシュートも撮り納めかな。
同じシステムは実はF-2にもあるそうだけど。
これで飛行展示はおしまい。
後は地上展示をぶらぶら見ながら代々木第一体育館に向かうことにする。


こちらは今回飛ばなかった展示機。

機体に描かれている年号は、ファントムがデビューしてから退役までの歳月。
艦艇だって30年そこそこが寿命というのに、これだけ長く使われているということは、やっぱり名機なんだろうなあ。
なお、百里は来年は航空観閲式。
再来年の航空祭では、F-2が代わってやってくるらしい。
というわけで百里を後にし、今度は代々木へ。
一緒に行く予定の妹と合流し、会場に入ったのだが、なんだか今回手荷物検査が厳しかった。
いつもはバッグのメイン部分をを開けてひととおり見せればおしまいなのだが、今回は収納可能な場所は全部開くように言われ、手を入れて中まで探られた。
百里基地で買った羊羹とかぎんなんとか芋がらとか(地元のおばちゃんが野菜や果物を商品に出店していたのだ)を晒す羽目になって非常に恥ずかしかったのは言うまでもない。

ちょっと時間が遅かったので2階席。
楽屋裏?で最後の練習をしている人たちが見える。

オープニング。
代々木体育館は会場を挟んで観客席が両側に分かれている。
正面は赤い貴賓席がある場所なので、基本的に演奏者はそちらに向かって演技をする。ちなみに今回座ったのは反対側。
一応、こんな風に反対側も向いてやってくれる場合もあるのだが、大体は演奏者の背中を見ることになる。

人文字「令和」。

陸自と儀仗隊。

海自は今回、ベートーヴェンのメドレーをピアノコンチェルトで演奏という変わった演目だった。
でも最後はいつもの通りの軍艦マーチだったけど。

在日米陸軍。

米海兵隊。


陸海空時と合同演奏。
楽しそうだ。


ゲストバンド、ベトナム人民軍総参謀部儀礼団軍楽隊。
国旗の星を人文字で描き、その名も「ベトナム」という歌を高らかに歌い上げる姿に、何というか確かに共産主義国家だなと納得してしまった。



こちらもゲストバンド、ドイツ連邦軍参謀軍楽隊。
ベルリン・フィルとも共演できるレベルの高さらしいが、それ以外にも人文字が非常に巧みだった。
3枚目で「日本♡」と書いてきたり、退場時には軍の紋章である鷲の姿を描いて羽ばたかせながら去っていったり、さすがベルリン・フィルのお膝元だけのことはある(違う)。
ちなみに妹がエーベルバッハ少佐と同じ制服だと感動していたが、そこか? そこなのか?

空自。
パターンは毎年一緒なのだが、毎回華やかに見せてくる演出力はやっぱりすごい。



ゲストバンドと陸海空勢揃い。米軍が相手の時とは違って今度はまじめ。
しかし真ん中の箱ドラムの意味が分からないのだが、何だろうか?

太鼓。


フィナーレ。


指揮者退場。
背中ばかり見る羽目になった割には、なかなか面白かった。
しかし、来年もここでやるなら、もうちょっと両面に配慮した構成にしてほしいな。

退場者の波。
一応流れてはいるようだが、あの状況だと会場の外は大混雑しているのではないだろうか。


とりあえずコロコロの儀式を見ながらすくのを待って帰ろう。